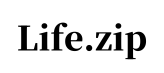遺伝子組み換え食品の普及が進んでいますが、安全性については議論が絶えません。遺伝子組み換え食品に不安を抱きながらも、日々の食事で知らぬ間に口にしている場合があります。遺伝子組み換え食品は、表示を見ないと区別がつきません。
当記事では、遺伝子組み換え食品の基本や危険性、利点を解説します。記事を読めば、遺伝子組み換え食品について正しい知識を得られ、健康と環境への影響を考慮した食品選びが可能です。
遺伝子組み換え食品の基本

遺伝子組み換え食品とは、遺伝子組み換え技術を用いて開発された作物及び作物を原料とする加工食品のことです。特定の生物から有用な性質を持つ遺伝子を取り出し、他の生物に組み込んで新しい性質を持たせます。遺伝子組み換え技術は、害虫や除草剤への耐性や栄養の向上などの利点があります。
安全性や環境への影響については不透明な部分も多いです。安全性や環境への影響を踏まえたうえで、消費者自身で摂取するか否かを判断する必要があります。遺伝子組み換え食品の種類や普及状況、ゲノム編集との違いを解説します。
遺伝子組み換え食品の種類
遺伝子組み換え食品に該当するのは、以下の加工食品です。
| 対象農産物 | 加工食品 |
| 大豆 (枝豆及び大豆もやしを含む) | 豆腐・油揚げ類、凍豆腐、おから及びゆば、納豆、豆乳類、みそ、大豆煮豆、大豆缶詰及び大豆瓶詰、きな粉、大豆いり豆 調理用の大豆を主な原材料とするもの 枝豆を主な原材料とするもの 大豆もやしを主な原材料とするもの |
| とうもろこし | コーンスナック菓子、コーンスターチ、ポップコーン、冷凍とうもろこし、とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰め コーンフラワーを原材料とするもの コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く) 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの |
| ばいれいしょ | ポテトスナック菓子、乾燥ばいれいしょ、冷凍ばいれいしょ、ばいれいしょでん粉、調理用のばいれいしょを原材料とするもの |
| アルファルファを主な原材料とする食品 | アルファルファを主な原料とするもの |
| みそ | トウモロコシ缶詰及びトウモロコシ瓶詰 |
| 大豆煮豆 | コーンフラワーを主な原材料とする食品 |
| てん菜 | 調理用のてん菜を主な原材料とするもの |
| パパイヤ | パパイヤを主な原材料とするもの |
| からしな | – |
遺伝子組み換え作物の大豆を使用した食品には、豆腐や納豆、みそやしょうゆなどがあります。キャノーラ油やマーガリンなども、遺伝子組み換え作物のなたねを使用しているケースが大半です。てん菜は、チョコレートやジューズなどの原材料として幅広く使用されています。
33種類もの加工食品が遺伝子組み換え食品に該当するため、知らないうちに摂取していることがあります。遺伝子組み換え食品を口にしないためには、国産の作物を使用した食品を選ぶことです。オリーブ油やごま油など、非遺伝子組み換え作物を原材料とする油を選ぶことも重要です。
遺伝子組み換え食品の普及状況

遺伝子組み換え食品の普及は、1996年の商業栽培開始以降、全世界に進んでいます。2023年時点での遺伝子組み換え作物の栽培面積は、世界26か国で2億600万ヘクタール以上に及びます。全世界の中でも、米国では7,440万ヘクタール以上の農地で、遺伝子組み換え作物を栽培しているのが現実です。
栽培面積の広い米国では、大豆の94%、トウモロコシの92%、綿花の94%が遺伝子組み換え作物となっています。ブラジルやアルゼンチン、インド、カナダなども遺伝子組み換え作物の主要生産国です。ブラジルでは、大豆の84%、トウモロコシの78%、綿花の50%が遺伝子組み換え作物となっています。
アルゼンチンでは大豆の95%、トウモロコシの90%が遺伝子組み換え作物に該当します。遺伝子組み換え食品の普及は全世界に進んでいますが、国によって異なるのが現状です。EU諸国では、遺伝子組み換え作物の栽培に厳しい規制が設けられているため、普及は限定的となっています。
日本では商業栽培は行われていませんが、海外からの輸入が進んでいます。海外で遺伝子組み換え作物の普及が進んでいるため、日本にも輸入されているのが現状です。
遺伝子組み換え食品の表示義務も国によって違い、米国は遺伝子組み換えの表示が任意で、EU諸国や日本では義務化されています。食料増産の必要性や農業の効率化などが要因となり、新興国や発展途上国での遺伝子組み換え作物の栽培が増加しています。
ゲノム編集と遺伝子組み換えの違い
ゲノム編集は特定の遺伝子のみを編集する技術で、遺伝子組み換えは特定の遺伝子のみを組み込む技術です。ゲノムとは、遺伝子と染色体から合成された言葉で、すべてのDNA遺伝情報のことを指します。近年では、さまざまな生物のゲノム情報が明らかになっています。
ゲノム編集はさまざまな生物のゲノム情報を利用し、遺伝子を切断したりつなげたりする技術です。DNA切断システムを利用して、狙った遺伝子だけを正確に編集できます。ゲノム編集は規制が緩いうえに開発期間も短縮できるため、コストをおさえられるのが特徴です。
遺伝子組み換えは、生物から目的の遺伝子を取り出し、別の生物のゲノムに導入することで、生物に新しい性質を付与する技術です。遺伝子を導入することで、他の遺伝子に予期せぬ影響が及んだり、予測不可能な結果が生じたりする可能性があります。
遺伝子組み換えは厳しい規制が設けられ、開発期間も長くかかるためコストもかかります。ゲノム編集と異なり、消費者の抵抗が強いのも遺伝子組み換えの特徴です。遺伝子組み換えよりゲノム編集のほうが、精密かつ効率的な遺伝子改変が可能です。
ゲノム編集にも遺伝子組み換えにも多くの課題があるため、食品の安全性については、慎重に検討する必要があります。
遺伝子組み換え食品の危険性

遺伝子組み換え食品の危険性を紹介します。
アレルギー反応
遺伝子組み換え食品において懸念されているのは、アレルギー反応です。既知アレルゲンとの交差反応や未知のアレルゲンの生成、特定のアレルギー体質の方への影響などが考えられます。アレルギー物質を含む食品には、物質の表示が義務付けられていますが、既存アレルゲン量が増加する可能性もあります。
アレルギー反応のリスク予測は困難です。アレルギーがある場合は、従来食品と同様に注意が必要です。
» オーガニックとは?製品の特徴を解説
遺伝子汚染

遺伝子組み換え食品の危険性として、遺伝子汚染も懸念されています。遺伝子汚染とは、遺伝子組み換え作物の遺伝子が意図せず、他の作物や野生種に伝染することです。遺伝子汚染は、生態系のバランスを崩す可能性があるため、多くの専門家が懸念を抱いています。
遺伝子汚染の主な形態と懸念事項は以下のとおりです。
- 野生種の交雑によって伝わる
- 花粉によって遺伝子が媒介する
- 交雑で従来種の遺伝的特徴性が失われる
- 除草剤では駆除できない雑草が生まれる
遺伝子汚染により、消費者が意図せず遺伝子組み換え食品を口にする恐れがあります。非遺伝子組み換え作物を栽培する農家にも、影響を与える可能性があります。遺伝子汚染は、物理的隔離や時間的隔離などで低減できますが、完全に防ぐのは困難です。今後も継続的な監視と研究が必要です。
抗生物質への耐性
遺伝子組み換え食品の危険性として、抗生物質への耐性も挙げられます。抗生物質耐性とは、細菌が抗生物質の効果に対して抵抗性を持つことです。抗生物質への耐性は、消費者の健康に直接影響を与える可能性があります。遺伝子組み換え作物の中には、抗生物質耐性遺伝子を含む作物があります。
問題は、抗生物質耐性遺伝子が人間の腸内細菌に移転することで、抗生物質耐性菌が増えることです。抗生物質耐性菌が増えれば、抗生物質の効果は得られません。抗生物質が効かなくなると、公衆衛生にも影響を及ぼします。
抗生物質耐性の問題は、家畜の飼育や農作業の栽培における過剰使用とも関連しています。抗生物質の過剰使用により、耐性菌の出現が促進する仕組みです。抗体物質耐性は、健康や環境への影響を踏まえて、今後も着目すべき問題です。
遺伝子組み換え食品の潜在的な危険性

遺伝子組み換え食品における潜在的な危険性を紹介します。
健康への影響
遺伝子組み換え食品における健康への影響は、十分なデータが蓄積されていないため不透明です。十分なデータが蓄積されていないのは、遺伝子組み換えが新しい技術であるためです。主な健康への影響として、以下が懸念されています。
- アレルゲンの発生につながる
- 作物の栄養価が変化する
- 腸内細菌そうのバランスに影響を与える
- ホルモンの働きを妨げる
一部の研究では、遺伝子組み換え食品に含まれるDNAが消化されず、人間の体内に吸収される可能性も指摘されています。科学的には、食中に含まれるDNAは消化過程で分解されると言われていますが、100%ではありません。現時点では、遺伝子組み換え食品が健康に影響を及ぼすか否かは不透明です。
消費者は、自分の判断で遺伝子組み換え食品の摂取を判断する必要があります。
環境への影響

遺伝子組み換え食品が環境に与える影響については、以下の懸念があります。
- 害虫や雑草の抵抗性獲得
- 非標準的生物への影響
- 土壌微生物への影響
- 農薬使用量の増加による土壌や水質汚染
花粉による周辺環境への遺伝子拡散や、遺伝子組み換え作物の野生化も問題視されていますが、影響の程度は不明です。遺伝子組み換え食品が環境に与える影響についても、不確実な部分が多いため、今後も継続的なモニタリングと研究が必要です。
生態系への影響
遺伝子組み換え作物の栽培は、生態系全体に影響を及ぼす可能性があります。生態系への影響として懸念されている状況は以下のとおりです。
- 生態系バランスの崩壊
- 遺伝子の拡散
- 土壌環境への影響
- 食物連鎖への影響
害虫抵抗性を持つ遺伝子組み換え作物の導入により、特定の害虫の個体数が減少します。害虫の個体数が減少すれば、特定の害虫を餌としていた天敵の減少につながり、生態系の食物連鎖に影響を与えかねません。遺伝子組み換え作物の栽培により、一部の遺伝子組み換え作物が野生化する可能性もあります。
遺伝子組み換え作物が野生化することで、生態系内で従来種と資源を巡る競合が起こり、駆逐する可能性も否めません。従来種の減少は、従来種に依存していた他の生物にも影響を及ぼし、生態系全体のバランスを崩します。遺伝子組み換え作物の栽培にも、長期的な研究とモニタリングが必要です。
遺伝子組み換え食品が人体以外に与える危険性

遺伝子組み換え食品が人体以外に与える危険性について紹介します。
農業に与える影響
遺伝子組み換え技術の導入により、農業のありかたを変える必要があります。除草剤耐性作物の普及により、除草剤の使用量が増加することで、環境への負荷が懸念されるからです。除草剤耐性を持つ雑草は、従来の農薬では対処できないため、新たな農薬を開発する必要もあります。
遺伝子組み換え種子が主流になれば、従来種子の入手が困難になるため、遺伝子組み換え種子を使用せざるを得ません。遺伝子組み換え種子が主流になることで、従来種子を使用した栽培方法や、伝統的な農業知識が失われる恐れもあります。
遺伝子組み換え作物と有機農業の共存は難しく、両者の境界をどのように設定し管理するのかも重要な課題です。遺伝子組み換え作物に付着している花粉が風や虫によって、有機作物と交雑する可能性があります。遺伝子汚染が起きた場合は、有機農産物の認証が無効になります。
遺伝子汚染は有機農家にとって、経営損失につながる問題です。遺伝子組み換え作物の栽培により農業に生じる問題に対しては、規則の規定や生産者間での協力が不可欠です。今後の持続可能な農業にとって、農業の多様性を維持しつつ、異なる栽培方法の共存を図ることが重要な課題となります。
» 農薬の害が気になる方必見!基本から注意点まで詳しく解説!
経済的に与える影響
遺伝子組み換え食品が経済に与える影響は、以下のとおりです。
- 食品価格の低下
- 農業市場の競争激化
- 貿易摩擦
- 研究開発費の増加
遺伝子組み換え作物は環境ストレス耐性を持つため、作物の収量が増加し、生産量が向上します。生産量が向上すれば、供給の増加につながるため、食品価格が低下します。遺伝子組み換え技術を持つ大企業が市場を独占しやすくなる点も問題です。大企業農家が市場を独占すれば、小規模農家が経済的に圧迫されます。
遺伝子組み換え食品の表示義務により、製造や流通コストが上昇する可能性もあります。コストの上昇は、消費者を守るために必要な措置ですが、企業に負担がかかるのが問題です。遺伝子組み換え作物に対する規制は国によって異なるため、遺伝子組み換え作物を大量に生産する国との間に貿易摩擦が生じます。
遺伝子組み換え食品の利点

遺伝子組み換え食品の利点は以下のとおりです。
- 食料問題を解決する可能性
- 作物の耐病性や耐久性の向上
食料問題を解決する可能性
遺伝子組み換え食品は以下の利点により、世界的な食料問題を解決する可能性があります。
- 収穫量の増加
- 食品保存期間の延長
- 栄養価の高い作物の開発
- 病害虫や環境ストレスに強い品種の作出
遺伝子組み換え技術は、食料自給率の向上や食品ロスの削減に役立ちます。遺伝子組み換え技術の活用により、従来の育種方法では困難だった特性を持つ作物の開発も可能です。作物の開発が可能になったことで、食料の多様性確保や環境負荷の軽減にも貢献できます。
作物の耐病性や耐久性の向上
遺伝子組み換え技術の利点は、作物の耐病性や耐久性を向上できることです。遺伝子組み換え技術により作物に与える利点は、以下のとおりです。
- 病害虫への抵抗性向上
- 環境ストレスへの耐性強化
- 低温や高温への適応能力の向上
- 貯蔵性の改善
- 長期保存の実現
作物の耐病性や耐久性が向上すれば、農薬の使用量を減らしたり、厳しい環境でも作物を育てたりできます。食料生産の安定化や環境への負荷軽減にもつながります。遺伝子組み換え技術は作物の改良に大きな可能性を持つ一方で、慎重な対応が求められる技術です。
安全性の確保と環境への配慮を忘れずに、技術の利点を生かすことが重要です。
» オーガニックと無農薬の違いは?自分に合った製品を選ぶ基準
遺伝子組み換え食品の危険性に関するよくある質問

遺伝子組み換え食品の危険性に関するよくある質問を紹介します。
遺伝子組み換え食品は自然のものと何が違う?
遺伝子組み換え食品と自然食品の違いは、以下のとおりです。
| 比較項目 | 遺伝子組み換え食品 | 自然食品 |
| 遺伝子の操作方法 | 人工的に特定の遺伝子を導入または改変している | 自然な交配や突然変異によって遺伝的変化が起こる |
| 特性の付与 | 新しい特性が付与される | 人工的な特性付与はない |
| 変化のスピード | 早い | 遅い |
| 表示義務 | 有 | 無 |
遺伝子組み換え食品と自然食品との違いを把握したうえで、自分に合った食品を選んでください。
遺伝子組み換え食品の安全性を評価する方法は?
遺伝子組み換え食品の安全性を評価する方法は、以下のとおりです。
- 動物に与え健康への影響を評価する
- 成分が過度に増減していないか確認する
- 栄養成分や有害物質の含有量を分析する
遺伝子組み換え食品の安全性は、複数の方法を組み合わせて総合的に判断する必要があります。遺伝子組み換え食品の安全性は、科学的知見にもとづいて実行され、食品安全委員会の専門家によって審査されます。安全な遺伝子組み換え食品のみが、日本での流通を許可される仕組みです。
遺伝子組み換え食品の安全性は、市販後も継続的に確認され、必要に応じて適切な措置が講じられています。
まとめ

遺伝子組み換え食品の危険性や利点などを解説しました。遺伝子組み換え食品の危険性は、可能性にとどまっており不透明なのが現状です。遺伝子組み換え食品の利点としては、食料供給の安定化や食品の品質向上などが挙げられます。遺伝子組み換え食品の種類は、大豆やじゃがいもなど、多岐にわたります。
遺伝子組み換え食品と従来食品の違いを把握したうえで、購入を判断することが重要です。科学的根拠をもとに冷静に考え、健康や環境への影響を考慮して食品を選びましょう。
» 食生活を整えるための栄養素と健康維持のポイント